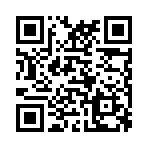2009年11月16日
藤枝桐箪笥の伝統 (静岡県・郷土伝統工芸品)
本日は、藤枝市本町にある「山田タンス店」を取材させていただきました!
桐ダンスといえば
「耐湿性」に優れ、「虫がつきにくく」、「熱を通しにくい」。
昔から貴重品や衣類の収納に重宝されてきたものです。
そして、藤枝の桐ダンスは静岡県の「郷土伝統工芸品」に指定されているんです!
ちょうど、中学生の体験授業が行われるということでおじゃましま~す。
教えてくださるのは、山田タンス店 三代目 山田美吉さん。

生徒さんたちが作るのは桐の箱。
カンナやキリ、木のくぎなど、普段はまったく手にすることのない道具を前に
「始めて使うー」と子供たち。
みんなどうしていいのか・・なかなか四苦八苦。

特に「カンナ」は難しい、「腰」や「腹」にしっかり力が入っていないとうまくいかない。
腹(はら)、肚(はら)、
考えてみると日本は「腹の文化」といわれるほど、「腹」や「腰」に重点をおきます
「腹が立つ」、「グッと腹におさめる」、「腹を決める」、「腹を割って話す」
「肝っ玉かあちゃん」「自腹を切る」「私腹を肥やす」・・・
精神面での強さや、その人の本質的なものが腹に宿っている。
という感じがしますよね。
農耕の文化の日本は舞踊でも、足や腰、腹などの大地へ向かう重量感
人体の中心、力の源となる「腹」や「腰」が大切にされています。
現在では生活スタイルも変わり、腰や腹への文化も変容していますが 。 。
でも、桐の小箱作りでは肝心! カンナが挑んできます。
腹に力はいってるかー?! 腰がしっかりしてるかー?!
箱を作るだけ・・とおもったら大変。
いろんなことを身体で学びます。

「すべて手仕事ですから、たいへんですよ。」
手仕事の大変さ、その価値を汲み取れる感性。 育てましょう。
桐タンスの美しさ、手触りのよさ・・
そして、釘!!

釘は木製で、1本1本手作り。
瀬戸谷まで行っての空木(うつぎ)という真ん中に穴が開いている木を取ってきて、1本いっぽん削ります。
そしてそれをを、ぬかで炒って、油を出します。
最近の木製の釘は、タンスに使うものなどでも丸い(円柱)のモノが多いですが、
楔形の釘を使うことで、ずれないし、ゆるまなくなるそうです。
この一本の釘を作るのが大変な作業なんですね~!!

「桐ダンスは湿気を吸い込む力が強いからね、米などの食べ物も入れることができる。
パンを入れたらラスクになっちゃったってねー!
消臭にも効果があるんだよ。」
そんなコミュニケーションのなかで、美吉さんはじめ、教えてくださる先生を頼りに
桐の箱が出来上がっていきます。
本来なら仕上げは「とのこ(石の粉)」を塗りますが、今回は次のサンドペーパーの仕上げへ。
この頃にはもう、安心感が漂ってきます。 良かった~。
伝統工芸のシールを貼って、名前を書いて。完成!!
出来上がりを比べあいながら、元気よくお礼を言って、桐の箱を自転車の籠に入れて
みんなが帰っていきました。
体験はお金では買えない貴重なものですが、
キリの箱も、買えば3~4千円。
大事にするんだよ~!!!
そんなこともこだわらず、丁寧に教えてくださる美吉さんと山田タンス店の方々は本当に懐が深い。
「職人なんてね~ 話し旨いわけじゃないんだから 笑
話聞いたってしょうがないねぇ
やっぱりやってみることが だいじ」
手仕事の技術とタンスが多くのことを教えてくれます。
藤枝の桐箪笥、伝統工芸の技術から学ぶことは多いです。
地域の大人はもちろんですが、子供たちが、こういった技術継承のことを知っていくのは大事ですね。
ぜひ、桐ダンスのお話を聞いて、その技を見てみてください。
◇
山田タンス店
静岡県知事指定 郷土伝統工芸品≪藤枝桐箪笥≫
〒426-0018
藤枝市本町1丁目5番16号
054-641-3800

山田美吉さん、山田タンス店の方々、ありがとうございました!
桐ダンスといえば
「耐湿性」に優れ、「虫がつきにくく」、「熱を通しにくい」。
昔から貴重品や衣類の収納に重宝されてきたものです。
そして、藤枝の桐ダンスは静岡県の「郷土伝統工芸品」に指定されているんです!
ちょうど、中学生の体験授業が行われるということでおじゃましま~す。
教えてくださるのは、山田タンス店 三代目 山田美吉さん。
生徒さんたちが作るのは桐の箱。
カンナやキリ、木のくぎなど、普段はまったく手にすることのない道具を前に
「始めて使うー」と子供たち。
みんなどうしていいのか・・なかなか四苦八苦。
特に「カンナ」は難しい、「腰」や「腹」にしっかり力が入っていないとうまくいかない。
腹(はら)、肚(はら)、
考えてみると日本は「腹の文化」といわれるほど、「腹」や「腰」に重点をおきます
「腹が立つ」、「グッと腹におさめる」、「腹を決める」、「腹を割って話す」
「肝っ玉かあちゃん」「自腹を切る」「私腹を肥やす」・・・
精神面での強さや、その人の本質的なものが腹に宿っている。
という感じがしますよね。
農耕の文化の日本は舞踊でも、足や腰、腹などの大地へ向かう重量感
人体の中心、力の源となる「腹」や「腰」が大切にされています。
現在では生活スタイルも変わり、腰や腹への文化も変容していますが 。 。
でも、桐の小箱作りでは肝心! カンナが挑んできます。
腹に力はいってるかー?! 腰がしっかりしてるかー?!
箱を作るだけ・・とおもったら大変。
いろんなことを身体で学びます。
「すべて手仕事ですから、たいへんですよ。」
手仕事の大変さ、その価値を汲み取れる感性。 育てましょう。
桐タンスの美しさ、手触りのよさ・・
そして、釘!!
釘は木製で、1本1本手作り。
瀬戸谷まで行っての空木(うつぎ)という真ん中に穴が開いている木を取ってきて、1本いっぽん削ります。
そしてそれをを、ぬかで炒って、油を出します。
最近の木製の釘は、タンスに使うものなどでも丸い(円柱)のモノが多いですが、
楔形の釘を使うことで、ずれないし、ゆるまなくなるそうです。
この一本の釘を作るのが大変な作業なんですね~!!
「桐ダンスは湿気を吸い込む力が強いからね、米などの食べ物も入れることができる。
パンを入れたらラスクになっちゃったってねー!
消臭にも効果があるんだよ。」
そんなコミュニケーションのなかで、美吉さんはじめ、教えてくださる先生を頼りに
桐の箱が出来上がっていきます。
本来なら仕上げは「とのこ(石の粉)」を塗りますが、今回は次のサンドペーパーの仕上げへ。
この頃にはもう、安心感が漂ってきます。 良かった~。
伝統工芸のシールを貼って、名前を書いて。完成!!
出来上がりを比べあいながら、元気よくお礼を言って、桐の箱を自転車の籠に入れて
みんなが帰っていきました。
体験はお金では買えない貴重なものですが、
キリの箱も、買えば3~4千円。
大事にするんだよ~!!!
そんなこともこだわらず、丁寧に教えてくださる美吉さんと山田タンス店の方々は本当に懐が深い。
「職人なんてね~ 話し旨いわけじゃないんだから 笑
話聞いたってしょうがないねぇ
やっぱりやってみることが だいじ」
手仕事の技術とタンスが多くのことを教えてくれます。
藤枝の桐箪笥、伝統工芸の技術から学ぶことは多いです。
地域の大人はもちろんですが、子供たちが、こういった技術継承のことを知っていくのは大事ですね。
ぜひ、桐ダンスのお話を聞いて、その技を見てみてください。
◇
山田タンス店
静岡県知事指定 郷土伝統工芸品≪藤枝桐箪笥≫
〒426-0018
藤枝市本町1丁目5番16号
054-641-3800
山田美吉さん、山田タンス店の方々、ありがとうございました!
Posted by MAITOM at 22:00
│工芸 ~Craft~