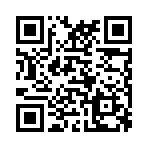2010年04月13日
岡部の旧道で藍染を楽しむ
今回ご紹介するのは藤枝市岡部町の
岡部の旧道沿いにある アトリエタカオ

ガラガラっと戸を開けると、奥から藍の風が ふっー と通るような気持ちの落ち着く空間。
入ったところにある昔ながらのつくりの家のつくりと囲炉裏に
思わずひとやすみしたくなってしまいます。

いつも笑顔で対応してくださるのは 染物屋3代目 増井隆夫さん。

いろんな方を案内する度に、建物の解説や藍のお話を丁寧にしてくださいます。
また、服のパターナーでもある隆夫さんの作品はとても綺麗な仕立てられていて
藍のシンプルさや表現を引き立て合っています。
岡部の総合案内所にもポスターが展示されているのでチェックしてみてくださいね。
また、短歌の先生でもあるとのことで!!
審査員として市外に出かけておられることもしばしば・・。
さて、この昔ながらの建築でもある増井さん宅には
染物に使うための工夫が随所に施されているんです。

反物を一反(一反というと、着物が一枚分。幅36cm×長11m) 張ることができる仕組みがあったり
藍甕の下には甕を暖めるための空間があったり
あっ!あそこに!!ホントだ~ と、その工夫の発見がなかなか楽しみでもあります。

ひらけた芝生の中庭をぬけると、なんと明治から!使用されているという藍甕染が8基。
漆黒の穴が8つ? ぬるりと艶っぽく光っています。

この藍甕の部屋の独特!!の香りが、私はなんとも言えず好きなのですが
体験に来る中学生や小学生には衝撃的のようです 笑
藍には藍の華が咲くって、皆さん知っていました?!
藍の甕に浮かんでいる泡の塊のようなもの これが藍の華。

これで藍の状態がわかるとのこと。
「華」だなんて、なんだか素敵な表現ですねー。
さて、今回は岡部中学の生徒さんが体験に来ています
今日は最終段階の「染」の時間!
藍の話や 藍甕に入る前の藍の塊を触ったり 匂いをかいだり
友達同士で笑いあいながら楽しく進行していきます

これまでデザインを考えたり、のり付けをしてきた布を ついに藍色に染めていきます。
先生や、増井さんご夫妻の教えのもと、その時はみんな真剣です。

染めて 干して を繰り返し・・・

最後は水の中にジャブジャブっと浸けて洗います。

余分なゴミや藍を洗い流すんですね。
干すとくっきりみんなの絵や文字 デザインが現れてきました。

うーん なかなか凝ったモノを作るなぁ~!!
なかなか みんなの発想力はすごい。
あっ。これはな何を描いたの??
そうかー。ファンになってるジャーニーズの・・ ライブとかに持ってけそうだね~ 笑
すばらしい作品がせいぞろいです。
みんなを送り出した後、増井ご夫妻やお手伝いに来てくれた方々が一息。
かれこれ10年以上も子供たちを受け入れて、体験授業を行っているそうですが
毎回 大変だけど楽しい とのことです。

そんな藍染め教室も、日々の藍の管理などの苦労の賜物。
「藍は生きものです。」
と言う隆夫さんは、いい藍色を出すために
毎日毎日・・何があっても欠かさず藍甕をかき混ぜては様子をうかがっています。
また、11月~3月は甕を暖めるためにヒーターを下に入れたりするそうで。
これは、もともとは籾殻(もみがら)などを入れて、煙を出して暖めていたとのことですよ。
なかなか藍の「ごきげん伺い」も楽ではないんですね。
肌に優しく、染め物としても古くから日本人に愛用されてきた藍染。
隆夫さんの工房では瞬間瞬間に変化する藍の色を楽しみながら、
オリジナルの藍染ストール等を作ることが出来ます。

独特の藍の香りに包まれて、その魅力に引き込まれてしまうひととき。
出来上がったらそのまま、優しい風に吹かれながら岡部の旧東海道を歩いてみるのも良いかもしれないですね。
また、工房では、布地や糸などを染め、服・小物などを作り販売しています。
近くにお出かけの際には、立ち寄ってみて下さいね。
◇
アトリエ・タカオ
〒421-1131 藤枝市岡部町内谷90
tel/ 054-667-0228

増井さんご夫妻、お手伝いの方、岡部中学校のみなさん ありがとうございました!
岡部の旧道沿いにある アトリエタカオ
ガラガラっと戸を開けると、奥から藍の風が ふっー と通るような気持ちの落ち着く空間。
入ったところにある昔ながらのつくりの家のつくりと囲炉裏に
思わずひとやすみしたくなってしまいます。
いつも笑顔で対応してくださるのは 染物屋3代目 増井隆夫さん。
いろんな方を案内する度に、建物の解説や藍のお話を丁寧にしてくださいます。
また、服のパターナーでもある隆夫さんの作品はとても綺麗な仕立てられていて
藍のシンプルさや表現を引き立て合っています。
岡部の総合案内所にもポスターが展示されているのでチェックしてみてくださいね。
また、短歌の先生でもあるとのことで!!
審査員として市外に出かけておられることもしばしば・・。
さて、この昔ながらの建築でもある増井さん宅には
染物に使うための工夫が随所に施されているんです。
反物を一反(一反というと、着物が一枚分。幅36cm×長11m) 張ることができる仕組みがあったり
藍甕の下には甕を暖めるための空間があったり
あっ!あそこに!!ホントだ~ と、その工夫の発見がなかなか楽しみでもあります。
ひらけた芝生の中庭をぬけると、なんと明治から!使用されているという藍甕染が8基。
漆黒の穴が8つ? ぬるりと艶っぽく光っています。
この藍甕の部屋の独特!!の香りが、私はなんとも言えず好きなのですが
体験に来る中学生や小学生には衝撃的のようです 笑
藍には藍の華が咲くって、皆さん知っていました?!
藍の甕に浮かんでいる泡の塊のようなもの これが藍の華。
これで藍の状態がわかるとのこと。
「華」だなんて、なんだか素敵な表現ですねー。
さて、今回は岡部中学の生徒さんが体験に来ています
今日は最終段階の「染」の時間!
藍の話や 藍甕に入る前の藍の塊を触ったり 匂いをかいだり
友達同士で笑いあいながら楽しく進行していきます
これまでデザインを考えたり、のり付けをしてきた布を ついに藍色に染めていきます。
先生や、増井さんご夫妻の教えのもと、その時はみんな真剣です。
染めて 干して を繰り返し・・・
最後は水の中にジャブジャブっと浸けて洗います。
余分なゴミや藍を洗い流すんですね。
干すとくっきりみんなの絵や文字 デザインが現れてきました。
うーん なかなか凝ったモノを作るなぁ~!!
なかなか みんなの発想力はすごい。
あっ。これはな何を描いたの??
そうかー。ファンになってるジャーニーズの・・ ライブとかに持ってけそうだね~ 笑
すばらしい作品がせいぞろいです。
みんなを送り出した後、増井ご夫妻やお手伝いに来てくれた方々が一息。
かれこれ10年以上も子供たちを受け入れて、体験授業を行っているそうですが
毎回 大変だけど楽しい とのことです。
そんな藍染め教室も、日々の藍の管理などの苦労の賜物。
「藍は生きものです。」
と言う隆夫さんは、いい藍色を出すために
毎日毎日・・何があっても欠かさず藍甕をかき混ぜては様子をうかがっています。
また、11月~3月は甕を暖めるためにヒーターを下に入れたりするそうで。
これは、もともとは籾殻(もみがら)などを入れて、煙を出して暖めていたとのことですよ。
なかなか藍の「ごきげん伺い」も楽ではないんですね。
肌に優しく、染め物としても古くから日本人に愛用されてきた藍染。
隆夫さんの工房では瞬間瞬間に変化する藍の色を楽しみながら、
オリジナルの藍染ストール等を作ることが出来ます。
独特の藍の香りに包まれて、その魅力に引き込まれてしまうひととき。
出来上がったらそのまま、優しい風に吹かれながら岡部の旧東海道を歩いてみるのも良いかもしれないですね。
また、工房では、布地や糸などを染め、服・小物などを作り販売しています。
近くにお出かけの際には、立ち寄ってみて下さいね。
◇
アトリエ・タカオ
〒421-1131 藤枝市岡部町内谷90
tel/ 054-667-0228
増井さんご夫妻、お手伝いの方、岡部中学校のみなさん ありがとうございました!
Posted by MAITOM at
22:00
│工芸 ~Craft~
2010年03月16日
鬼瓦&スマイル
今回取材させていただいたのは、平島にある 渡邊商店さん!
あの、自動車学校に行く途中の、道がぐわーっと曲がっているところにある。。
というとわかる方も多いですね 笑。
本日は、ここの鬼瓦の工房である「郷倉窯」での陶芸教室におじゃましに参りました。
が、ここの渡邊社長さんに会わずには居られません。
そう、鬼瓦のような迫力!!? の社長です。

いえいえ、 この笑顔で、鬼も人も一緒に笑って 福を呼んでしまいそうです。
豪快!!!熱い!! しかしとても細かい気配り、それでいてハイセンス!な渡邊社長。
北から南へ、国内ばかりか、ニュージーランドの茶室やアメリカ・オマハへの仕事など
海外でも大仕事をしている渡邊社長は
いつも本当に色々な面白いお話をしてくださって、
アメリカ現代アートから日本画まで幅ひろーーーーい語りで、常に新しい世界を見せてくれます。
そんな社長が今日はぐるりと案内をしてくださいました。
瓦と言えば、いまはあまり使っていないお宅が多いですね。
さらには鬼瓦ともなると、思い浮かぶのは やはりお寺さんです。
沖縄にはシーサーをのっけてるお宅など多いですが・・(これも鬼瓦と同じ流れでしょうか??)
ということで、気になって少し調べてみると ・ ・ ・
なんと、
ルーツはパルミラ(シリア中央部)にて入口の上にメドゥーサ(あの髪の毛が蛇の・・)を厄除けとして設置したものだそうです!!
それがシルクロード経由で中国に伝来。
日本では奈良時代に唐文化を積極的に取り入れだした頃、急速に全国に普及したそうです。
寺院は勿論、一般家屋など比較的古い和式建築に多く見られ、
ご存知のように、平成期以降に建てられた建築物には見られることが少なくなりました。
(より詳しい情報は こちら ⇒ )
)
鬼瓦を作る職人は、ズバリ「鬼師」!
「鬼師」という職があるのですねー。
とにかくも、渡邊社長に聞けば、
静岡では、国分寺を作るのに大工や瓦師がきて住み着いてそこに住んだコトが始まり。
久能山のふもとにはお寺がいっぱいあったそうです。
鬼瓦ももちろんその流れと一緒にやってきました。
我が国で最も古い鬼瓦は、奈良県奥山久米寺のもので、
飛鳥時代後期のものと推測されるそうです!!
その後、鎌倉時代は獣面や鬼面が多く、
室町時代には、二本の角を持つ鬼面が多くなったそうです。
この辺になると立体的で また迫力があります。
桃山時代から鬼面がリアルになってきて、足元が次第に発達。
江戸時代になると、雲や植物や浪を図案化したものが現れ、
現在見るような鬼瓦の原型ができたとのこと。
その後の、室町時代以降になってから 全国の寺院や町屋で見るようになっていったそうですよ。
鬼瓦といってもいろんな種類があるんですねー
いろんな鬼瓦の写真は ⇒ でどうぞ!
でどうぞ!
これが結構、見ていると面白い。
おもしろいっっ!!
バリのお面に見えたり カナダのトーテムポールに見えたり 離島のお祭りの面にみえたり・・
興味は尽きませんが
そんなフツフツとしたイメージに取り付かれながら、付いていくと
事務所の横に小さなギャラリーがありました!!

ここは若手3人の陶芸作家さんの作品が展示されているギャラリー。

かわいらしいものから 素朴だけどグッとくるものまで 結構たくさんありますよ~。
これでパスタ食べたら美味しそうだなぁ
これはおひたしが合いそう
これで緑茶 飲みたいな~
と、それぞれの作品を楽しく拝見させていただきました。
作家さんモノを買うということは、普段だとなかなかナイ機会かもしれませんが
こうやってプロフィールやエピソードなどを聞きながら 器を手にとって 眺めて ・ ・
というもの 物のストーリーが見えてきて いろんな視点から楽しむことができます。
「自分で値段を決めているうちは駄目」
と、作家と買い手の仲介や 価格設定を引き受けているのが渡邊社長。
なるほど、確かに。。
さて、このギャラリー、一般の方でも購入可能!
ですので、ぜひ立ち寄ってみてくださいね。
これは!と 自分のお気に入りに出会ってしまうかもしれませんよ~!
また、ギャラリー内には
有名な陶芸作家の方の作品も一緒に展示してあったするので、
これ見たことある~!この作家さんの作品そういえば・・ と思い当たるかたも多いのでは。。
ギャラリー内をあれやこれやと
ひととおり拝見させていただき、 さてさて道を挟はさんで 隣の陶芸教室へ ・ ・ ・
と思ったら、 おや?
目に入ったのは ふと前の敷地にある赤いトラック。

おお~っ。
真っ赤っ!! トラックっ!!! ベンツっ!!!!
専門知識がないので マニアの方に是非解説していただきたいのですが
こんなトラック、ありなんですね。。
金額は ・ ・ ・ 伏せておきましょう。
ぐああああっっ と口をあけた姿がなんともスゴイ!!
これはもう、真っ赤な巨大生物 と言っても良いのかもしれません。

渡邊社長も負けてなーい!!
これでゲリラライブなんてしたらものすごい注目度。まちがいなし。
このドライバーさん、トラック仲間のあいだでは羨まれる存在だそうで。
「これ乗ってるから 給料要らないぐらいだよな~ 笑」
「ほしいっす」
なんて。 笑いながら。
テクテク後ろへ回ってみると ・ ・ !!

Of course I'm slower than you.
I'm carrying your dreams.
これは遅くてもしょうがない!と思ってしまいますね!!
大切に「夢」運んでください~ ♪
さて、操縦士の名前入り 巨大生物に圧倒されながらも。
いざ陶芸教室へ。
と、この先は次回に紹介させていただきましょう ・ ・
>>> 郷倉窯de陶芸 前田直紀さん へ続く。。

渡邊社長、渡邊商店の方々、ありがとうございました!
オマケ/
不思議なことに、この取材の前日に
スローライフ掛川さんの方におじゃまして
「カメラマン」から「カワラマン」に転身した 山田修二さん にお会いすることができたので!
瓦つながりで紹介させていただきます!
瓦の魅力 淡路島の魅力 どうぞ。
↓

写真を通して伝わってくる 淡路島の空気感と時間の流れ。
藤枝の風景や人物もこんな風にして表現できるなら ・ ・
と、思うのです。
あの、自動車学校に行く途中の、道がぐわーっと曲がっているところにある。。
というとわかる方も多いですね 笑。
本日は、ここの鬼瓦の工房である「郷倉窯」での陶芸教室におじゃましに参りました。
が、ここの渡邊社長さんに会わずには居られません。
そう、鬼瓦のような迫力!!? の社長です。
いえいえ、 この笑顔で、鬼も人も一緒に笑って 福を呼んでしまいそうです。
豪快!!!熱い!! しかしとても細かい気配り、それでいてハイセンス!な渡邊社長。
北から南へ、国内ばかりか、ニュージーランドの茶室やアメリカ・オマハへの仕事など
海外でも大仕事をしている渡邊社長は
いつも本当に色々な面白いお話をしてくださって、
アメリカ現代アートから日本画まで幅ひろーーーーい語りで、常に新しい世界を見せてくれます。
そんな社長が今日はぐるりと案内をしてくださいました。
瓦と言えば、いまはあまり使っていないお宅が多いですね。
さらには鬼瓦ともなると、思い浮かぶのは やはりお寺さんです。
沖縄にはシーサーをのっけてるお宅など多いですが・・(これも鬼瓦と同じ流れでしょうか??)
ということで、気になって少し調べてみると ・ ・ ・
なんと、
ルーツはパルミラ(シリア中央部)にて入口の上にメドゥーサ(あの髪の毛が蛇の・・)を厄除けとして設置したものだそうです!!
それがシルクロード経由で中国に伝来。
日本では奈良時代に唐文化を積極的に取り入れだした頃、急速に全国に普及したそうです。
寺院は勿論、一般家屋など比較的古い和式建築に多く見られ、
ご存知のように、平成期以降に建てられた建築物には見られることが少なくなりました。
(より詳しい情報は こちら ⇒
 )
)鬼瓦を作る職人は、ズバリ「鬼師」!
「鬼師」という職があるのですねー。
とにかくも、渡邊社長に聞けば、
静岡では、国分寺を作るのに大工や瓦師がきて住み着いてそこに住んだコトが始まり。
久能山のふもとにはお寺がいっぱいあったそうです。
鬼瓦ももちろんその流れと一緒にやってきました。
我が国で最も古い鬼瓦は、奈良県奥山久米寺のもので、
飛鳥時代後期のものと推測されるそうです!!
その後、鎌倉時代は獣面や鬼面が多く、
室町時代には、二本の角を持つ鬼面が多くなったそうです。
この辺になると立体的で また迫力があります。
桃山時代から鬼面がリアルになってきて、足元が次第に発達。
江戸時代になると、雲や植物や浪を図案化したものが現れ、
現在見るような鬼瓦の原型ができたとのこと。
その後の、室町時代以降になってから 全国の寺院や町屋で見るようになっていったそうですよ。
鬼瓦といってもいろんな種類があるんですねー
いろんな鬼瓦の写真は ⇒
 でどうぞ!
でどうぞ! これが結構、見ていると面白い。
おもしろいっっ!!
バリのお面に見えたり カナダのトーテムポールに見えたり 離島のお祭りの面にみえたり・・
興味は尽きませんが
そんなフツフツとしたイメージに取り付かれながら、付いていくと
事務所の横に小さなギャラリーがありました!!
ここは若手3人の陶芸作家さんの作品が展示されているギャラリー。
かわいらしいものから 素朴だけどグッとくるものまで 結構たくさんありますよ~。
これでパスタ食べたら美味しそうだなぁ
これはおひたしが合いそう
これで緑茶 飲みたいな~
と、それぞれの作品を楽しく拝見させていただきました。
作家さんモノを買うということは、普段だとなかなかナイ機会かもしれませんが
こうやってプロフィールやエピソードなどを聞きながら 器を手にとって 眺めて ・ ・
というもの 物のストーリーが見えてきて いろんな視点から楽しむことができます。
「自分で値段を決めているうちは駄目」
と、作家と買い手の仲介や 価格設定を引き受けているのが渡邊社長。
なるほど、確かに。。
さて、このギャラリー、一般の方でも購入可能!
ですので、ぜひ立ち寄ってみてくださいね。
これは!と 自分のお気に入りに出会ってしまうかもしれませんよ~!
また、ギャラリー内には
有名な陶芸作家の方の作品も一緒に展示してあったするので、
これ見たことある~!この作家さんの作品そういえば・・ と思い当たるかたも多いのでは。。
ギャラリー内をあれやこれやと
ひととおり拝見させていただき、 さてさて道を挟はさんで 隣の陶芸教室へ ・ ・ ・
と思ったら、 おや?
目に入ったのは ふと前の敷地にある赤いトラック。
おお~っ。
真っ赤っ!! トラックっ!!! ベンツっ!!!!
専門知識がないので マニアの方に是非解説していただきたいのですが
こんなトラック、ありなんですね。。
金額は ・ ・ ・ 伏せておきましょう。
ぐああああっっ と口をあけた姿がなんともスゴイ!!
これはもう、真っ赤な巨大生物 と言っても良いのかもしれません。
渡邊社長も負けてなーい!!
これでゲリラライブなんてしたらものすごい注目度。まちがいなし。
このドライバーさん、トラック仲間のあいだでは羨まれる存在だそうで。
「これ乗ってるから 給料要らないぐらいだよな~ 笑」
「ほしいっす」
なんて。 笑いながら。
テクテク後ろへ回ってみると ・ ・ !!
Of course I'm slower than you.
I'm carrying your dreams.
これは遅くてもしょうがない!と思ってしまいますね!!
大切に「夢」運んでください~ ♪
さて、操縦士の名前入り 巨大生物に圧倒されながらも。
いざ陶芸教室へ。
と、この先は次回に紹介させていただきましょう ・ ・
>>> 郷倉窯de陶芸 前田直紀さん へ続く。。
渡邊社長、渡邊商店の方々、ありがとうございました!
オマケ/
不思議なことに、この取材の前日に
スローライフ掛川さんの方におじゃまして
「カメラマン」から「カワラマン」に転身した 山田修二さん にお会いすることができたので!
瓦つながりで紹介させていただきます!
瓦の魅力 淡路島の魅力 どうぞ。
↓

写真を通して伝わってくる 淡路島の空気感と時間の流れ。
藤枝の風景や人物もこんな風にして表現できるなら ・ ・
と、思うのです。
Posted by MAITOM at
22:00
│工芸 ~Craft~
2009年11月16日
藤枝桐箪笥の伝統 (静岡県・郷土伝統工芸品)
本日は、藤枝市本町にある「山田タンス店」を取材させていただきました!
桐ダンスといえば
「耐湿性」に優れ、「虫がつきにくく」、「熱を通しにくい」。
昔から貴重品や衣類の収納に重宝されてきたものです。
そして、藤枝の桐ダンスは静岡県の「郷土伝統工芸品」に指定されているんです!
ちょうど、中学生の体験授業が行われるということでおじゃましま~す。
教えてくださるのは、山田タンス店 三代目 山田美吉さん。

生徒さんたちが作るのは桐の箱。
カンナやキリ、木のくぎなど、普段はまったく手にすることのない道具を前に
「始めて使うー」と子供たち。
みんなどうしていいのか・・なかなか四苦八苦。

特に「カンナ」は難しい、「腰」や「腹」にしっかり力が入っていないとうまくいかない。
腹(はら)、肚(はら)、
考えてみると日本は「腹の文化」といわれるほど、「腹」や「腰」に重点をおきます
「腹が立つ」、「グッと腹におさめる」、「腹を決める」、「腹を割って話す」
「肝っ玉かあちゃん」「自腹を切る」「私腹を肥やす」・・・
精神面での強さや、その人の本質的なものが腹に宿っている。
という感じがしますよね。
農耕の文化の日本は舞踊でも、足や腰、腹などの大地へ向かう重量感
人体の中心、力の源となる「腹」や「腰」が大切にされています。
現在では生活スタイルも変わり、腰や腹への文化も変容していますが 。 。
でも、桐の小箱作りでは肝心! カンナが挑んできます。
腹に力はいってるかー?! 腰がしっかりしてるかー?!
箱を作るだけ・・とおもったら大変。
いろんなことを身体で学びます。

「すべて手仕事ですから、たいへんですよ。」
手仕事の大変さ、その価値を汲み取れる感性。 育てましょう。
桐タンスの美しさ、手触りのよさ・・
そして、釘!!

釘は木製で、1本1本手作り。
瀬戸谷まで行っての空木(うつぎ)という真ん中に穴が開いている木を取ってきて、1本いっぽん削ります。
そしてそれをを、ぬかで炒って、油を出します。
最近の木製の釘は、タンスに使うものなどでも丸い(円柱)のモノが多いですが、
楔形の釘を使うことで、ずれないし、ゆるまなくなるそうです。
この一本の釘を作るのが大変な作業なんですね~!!

「桐ダンスは湿気を吸い込む力が強いからね、米などの食べ物も入れることができる。
パンを入れたらラスクになっちゃったってねー!
消臭にも効果があるんだよ。」
そんなコミュニケーションのなかで、美吉さんはじめ、教えてくださる先生を頼りに
桐の箱が出来上がっていきます。
本来なら仕上げは「とのこ(石の粉)」を塗りますが、今回は次のサンドペーパーの仕上げへ。
この頃にはもう、安心感が漂ってきます。 良かった~。
伝統工芸のシールを貼って、名前を書いて。完成!!
出来上がりを比べあいながら、元気よくお礼を言って、桐の箱を自転車の籠に入れて
みんなが帰っていきました。
体験はお金では買えない貴重なものですが、
キリの箱も、買えば3~4千円。
大事にするんだよ~!!!
そんなこともこだわらず、丁寧に教えてくださる美吉さんと山田タンス店の方々は本当に懐が深い。
「職人なんてね~ 話し旨いわけじゃないんだから 笑
話聞いたってしょうがないねぇ
やっぱりやってみることが だいじ」
手仕事の技術とタンスが多くのことを教えてくれます。
藤枝の桐箪笥、伝統工芸の技術から学ぶことは多いです。
地域の大人はもちろんですが、子供たちが、こういった技術継承のことを知っていくのは大事ですね。
ぜひ、桐ダンスのお話を聞いて、その技を見てみてください。
◇
山田タンス店
静岡県知事指定 郷土伝統工芸品≪藤枝桐箪笥≫
〒426-0018
藤枝市本町1丁目5番16号
054-641-3800

山田美吉さん、山田タンス店の方々、ありがとうございました!
桐ダンスといえば
「耐湿性」に優れ、「虫がつきにくく」、「熱を通しにくい」。
昔から貴重品や衣類の収納に重宝されてきたものです。
そして、藤枝の桐ダンスは静岡県の「郷土伝統工芸品」に指定されているんです!
ちょうど、中学生の体験授業が行われるということでおじゃましま~す。
教えてくださるのは、山田タンス店 三代目 山田美吉さん。
生徒さんたちが作るのは桐の箱。
カンナやキリ、木のくぎなど、普段はまったく手にすることのない道具を前に
「始めて使うー」と子供たち。
みんなどうしていいのか・・なかなか四苦八苦。
特に「カンナ」は難しい、「腰」や「腹」にしっかり力が入っていないとうまくいかない。
腹(はら)、肚(はら)、
考えてみると日本は「腹の文化」といわれるほど、「腹」や「腰」に重点をおきます
「腹が立つ」、「グッと腹におさめる」、「腹を決める」、「腹を割って話す」
「肝っ玉かあちゃん」「自腹を切る」「私腹を肥やす」・・・
精神面での強さや、その人の本質的なものが腹に宿っている。
という感じがしますよね。
農耕の文化の日本は舞踊でも、足や腰、腹などの大地へ向かう重量感
人体の中心、力の源となる「腹」や「腰」が大切にされています。
現在では生活スタイルも変わり、腰や腹への文化も変容していますが 。 。
でも、桐の小箱作りでは肝心! カンナが挑んできます。
腹に力はいってるかー?! 腰がしっかりしてるかー?!
箱を作るだけ・・とおもったら大変。
いろんなことを身体で学びます。
「すべて手仕事ですから、たいへんですよ。」
手仕事の大変さ、その価値を汲み取れる感性。 育てましょう。
桐タンスの美しさ、手触りのよさ・・
そして、釘!!
釘は木製で、1本1本手作り。
瀬戸谷まで行っての空木(うつぎ)という真ん中に穴が開いている木を取ってきて、1本いっぽん削ります。
そしてそれをを、ぬかで炒って、油を出します。
最近の木製の釘は、タンスに使うものなどでも丸い(円柱)のモノが多いですが、
楔形の釘を使うことで、ずれないし、ゆるまなくなるそうです。
この一本の釘を作るのが大変な作業なんですね~!!
「桐ダンスは湿気を吸い込む力が強いからね、米などの食べ物も入れることができる。
パンを入れたらラスクになっちゃったってねー!
消臭にも効果があるんだよ。」
そんなコミュニケーションのなかで、美吉さんはじめ、教えてくださる先生を頼りに
桐の箱が出来上がっていきます。
本来なら仕上げは「とのこ(石の粉)」を塗りますが、今回は次のサンドペーパーの仕上げへ。
この頃にはもう、安心感が漂ってきます。 良かった~。
伝統工芸のシールを貼って、名前を書いて。完成!!
出来上がりを比べあいながら、元気よくお礼を言って、桐の箱を自転車の籠に入れて
みんなが帰っていきました。
体験はお金では買えない貴重なものですが、
キリの箱も、買えば3~4千円。
大事にするんだよ~!!!
そんなこともこだわらず、丁寧に教えてくださる美吉さんと山田タンス店の方々は本当に懐が深い。
「職人なんてね~ 話し旨いわけじゃないんだから 笑
話聞いたってしょうがないねぇ
やっぱりやってみることが だいじ」
手仕事の技術とタンスが多くのことを教えてくれます。
藤枝の桐箪笥、伝統工芸の技術から学ぶことは多いです。
地域の大人はもちろんですが、子供たちが、こういった技術継承のことを知っていくのは大事ですね。
ぜひ、桐ダンスのお話を聞いて、その技を見てみてください。
◇
山田タンス店
静岡県知事指定 郷土伝統工芸品≪藤枝桐箪笥≫
〒426-0018
藤枝市本町1丁目5番16号
054-641-3800
山田美吉さん、山田タンス店の方々、ありがとうございました!
Posted by MAITOM at
22:00
│工芸 ~Craft~